【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,電力系統の信頼度に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切な語句を解答群の中から選び,その記号を記述用紙の解答欄に記入しなさい。
電力供給に関する品質を表す基本的項目としては,一般に電圧変動,\( \ \fbox { (1) } \ \)変動,停電の三つが用いられるが,この中で社会的影響が最も大きいのが停電,すなわち供給支障であり,この度合を表す尺度は一般的に\( \ \fbox { (2) } \ \)と呼ばれている。この\( \ \fbox { (2) } \ \)には,需要家側からみた表し方と供給者側からみた表し方がある。
需要家側からみた\( \ \fbox { (2) } \ \)の一般的な表し方としては,需要家一軒当たりの年間平均の停電回数と\( \ \fbox { (3) } \ \)が用いられる。また,供給者側からみた\( \ \fbox { (2) } \ \)の一般的な表し方としては,電源の供給力,最大需要電力等を確定論的に取り扱った\( \ \fbox { (4) } \ \)がある。電源の供給力のうち,水力発電については\( \ \fbox { (5) } \ \)を統計的に処理した供給力が採用されている。
\( \ \fbox { (4) } \ \)は電力輸送設備の事故等による電源の停止は考慮していない。このため,電力輸送設備の計画及び運用面に当たっては,一般に送電線の\( \ 1 \ \)回線事故,変電所の\( \ 1 \ \)バンク事故等の単一事故を想定しても,供給支障事故や電源脱落事故に至らないことを基準としている。また,重要系統については\( \ \fbox { (6) } \ \)事故等のより厳しい事故条件を想定して,この場合に供給支障や\( \ \fbox { (7) } \ \)の大きさ\( \ \mathrm {[kW]} \ \)や継続時間が許容されるレベルを超えることがないように電力輸送設備の構成を行っている。
〔問6の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 出水率 &(ロ)& 限界調整電力 &(ハ)& 電力不足確率 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 電 流 &(ホ)& 供給信頼度 &(ヘ)& 再閉路成功 \\[ 5pt ]
&(ト)& 定態安定度 &(チ)& 需要率 &(リ)& 多 重 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 力 率 &(ル)& 発電支障 &(ヲ)& 無効電力 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 出水変動 &(カ)& 単 一 &(ヨ)& 停電時間 \\[ 5pt ]
&(タ)& 周波数 &(レ)& 過渡安定度 &(ツ)& 理論包蔵水力 \\[ 5pt ]
&(ネ)& 供給予備率 &(ナ)& 電気料金 &(ム)& 事故件数 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電力系統の信頼度に関する問題です。
前半は信頼度の知識がある程度必要ですが,後半は知識がなくても国語力である程度カバーできる空欄となっています。本番でも諦めずに選択肢を絞って正答を導き出すようにして下さい。
1.供給信頼度
停電をせずに電力を需要家に供給できるかの信頼度を表す指標で,需要家側から見た信頼度と供給側から見た信頼度があります。
①需要家側から見た供給信頼度
実際に起こった停電時間と回数からの信頼度です。日本は諸外国と比べて停電時間,回数とも少ないという特徴があります。
②供給者側から見た供給信頼度
需要家側から見た供給信頼度に加え,停電リスクも踏まえた信頼度で確定論的な評価と確率論的な評価があります。
確定論的な評価としてはある一つの設備が故障した際でも供給支障が発生しないという基準を以て評価する\( \ \left( \mathrm {n-1} \right) \ \)基準という方法,確率論的な評価としては設備故障の発生確率や需要変動の確率等を考慮して評価する方法があります。
2.供給予備力と供給予備率
日々の電力需要は気象状況,平日・休日等から予想しますが,夏場予想以上に気温が上昇したり,冬場予想以上に低下したりすると需要は大きく増加します。その際の受給逼迫を防ぐため,発電設備の供給力にはある程度の余裕を持って運用しています。これを供給予備力といい,
供給予備力=発電設備の供給可能電力-予想電力
で求められます。近年では太陽光発電をはじめとした分散型電源の普及に伴い,気象状況により需要だけでなく発電電力も変化するようになっていますし,突発的な事故や水力発電所の出水変動等による供給力低下が発生する可能性もあるので,その辺りも考慮し供給予備力は設定されます。
また,供給予備力の予想電力に対する割合を供給予備率といい,
供給予備率=(供給予備力/予想電力)×100
で求められ,供給予備率が5%以下になると電力逼迫注意報,3%以下になると電力逼迫警報が発令されます。
一方で供給予備率が大きすぎても設備の無駄,コストアップに繋がってしまうため,安定供給ができる範囲で小さく抑えることが重要となります。
供給予備率は一般にエリアを小さくすれば地域毎に供給予備力の確保が必要となり,大きくなってしまいます。地域毎の大小も生じてしまいますので,できるだけエリアを大きくすることが合理的です。したがって,地域間連系線の容量を大きくし広域的な連系を行えば,地域間の電力融通を行うことが可能となり,全体として供給予備力を小さくすることが可能となるため,近年では地域間連系線の増強が進められています。
【解答】
(1)解答:タ
題意より解答候補は,(ニ)電流,(ヌ)力率,(ヲ)無効電力,(タ)周波数,等になると思います。
このうち,電力の品質を表す項目としては,電圧変動,周波数変動,停電があり,電気事業法でも電圧及び周波数の値を経済産業省令(電気事業法施行規則)で定める値に維持しなければならないと規定されています。
(2)解答:ホ
題意より解答候補は,(ハ)電力不足確率,(ホ)供給信頼度,(ト)定態安定度,(レ)過渡安定度,(ネ)供給予備率,等になると思います。
ワンポイント解説「1.供給信頼度」の通り,停電の度合を表す尺度は一般的に供給信頼度と呼ばれます。
(3)解答:ヨ
題意より解答候補は,(ヨ)停電時間,(ナ)電気料金,(ム)事故件数,等になると思います。
ワンポイント解説「1.供給信頼度」の通り,需要家側からみた供給信頼度の一般的な表し方としては,需要家一軒当たりの年間平均の停電回数と停電時間が用いられます。
(4)解答:ネ
題意より解答候補は,(ロ)限界調整電力,(ハ)電力不足確率,(ホ)供給信頼度,(ト)定態安定度,(チ)需要率,(レ)過渡安定度,(ネ)供給予備率,等になると思います。
ワンポイント解説「1.供給信頼度」及び「2.供給予備力と供給予備率」の通り,供給者側からみた供給信頼度の一般的な表し方としては,電源の供給力,最大需要電力等を確定論的に取り扱った供給予備率があります。
(5)解答:ワ
題意より解答候補は,(イ)出水率,(ワ)出水変動,(ツ)理論包蔵水力,になると思います。
ワンポイント解説「2.供給予備力と供給予備率」電源の供給力のうち,水力発電については出水変動を統計的に処理した供給力が採用されています。
(6)解答:リ
題意より解答候補は,(リ)多重,(カ)単一,になると思います。
重要系統については送電線の\( \ 1 \ \)回線事故,変電所の\( \ 1 \ \)バンク事故等の単一事故のみでなく多重事故等のより厳しい事故条件を想定します。
(7)解答:ル
題意より解答候補は,(ロ)限界調整電力,(ル)発電支障,等になると思います。
重要系統については多重事故等のより厳しい事故条件を想定して,供給支障や発電支障の大きさ\( \ \mathrm {[kW]} \ \)や継続時間が許容されるレベルを超えることがないように電力輸送設備の構成を行っています。
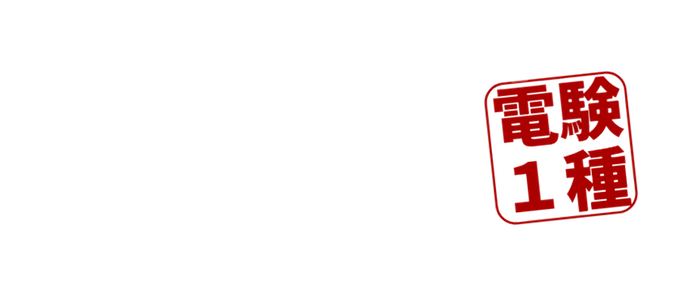
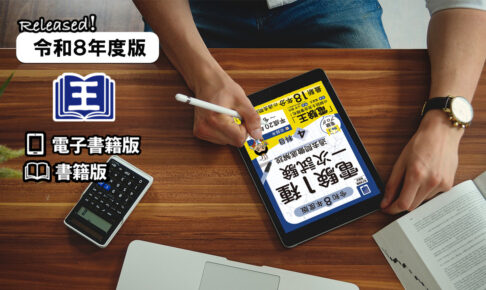
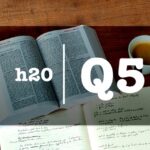

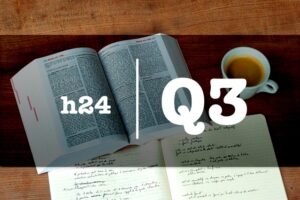
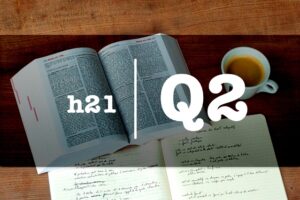
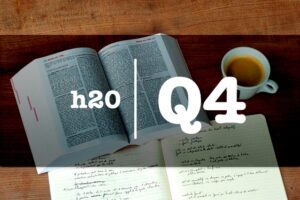
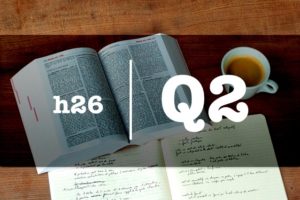
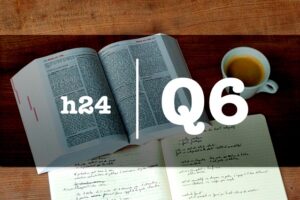
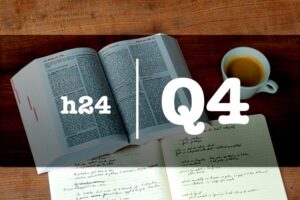
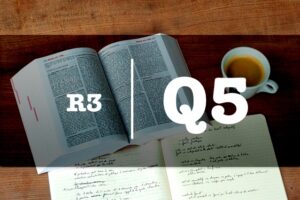
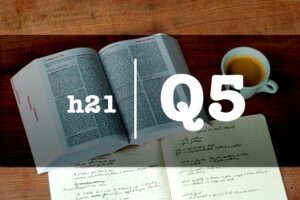

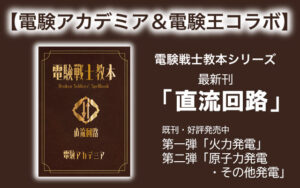
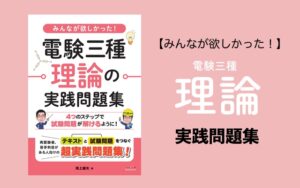
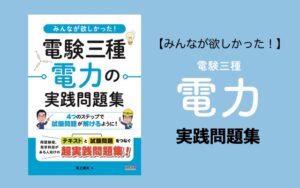
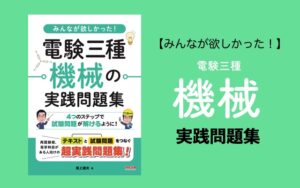
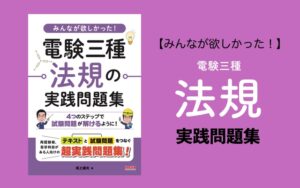




 愛知県出身 愛称たけちゃん
愛知県出身 愛称たけちゃん