【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章のうち,aとbは「電気設備技術基準」,cとdは「電気設備技術基準の解釈」に基づく,支持物の倒壊防止に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。
a.架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は,当該支線に係るものを含む。)は,その支持物が支持する電線等による引張荷重,風速\( \ 40 \ \mathrm {m/秒} \ \)の風速荷重及び当該設置場所において通常想定される気象の変化,\( \ \fbox { (1) } \ \),衝撃その他の外部環境の影響を考慮し,倒壊のおそれがないよう,安全なものでなければならない。ただし,人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては,その施設場所を考慮して施設する場合は,風速\( \ 40 \ \mathrm {m/秒} \ \)の風圧荷重の\( \ \fbox { (2) } \ \)の風圧荷重を考慮して施設することができる。
b.特別高圧架空電線路の支持物は,\( \ \fbox { (3) } \ \)等により連鎖的に倒壊のおそれがないように施設しなければならない。
c.架空電線路の支持物の基礎の安全率は,鉄塔を使用する場合にあっては,電気設備技術基準の解釈において当該支持物が耐えることと規定された荷重が加わった状態において\( \ \fbox { (4) } \ \)以上(鉄塔における異常時想定荷重又は異常着雪時想定荷重については,\( \ 1.33 \ \)以上)であること。
d.特別高圧架空電線路の支持物に,\( \ \fbox { (5) } \ \)を使用する鉄塔を連続して使用する部分は,\( \ \fbox { (6) } \ \)基以下ごとに,異常時想定荷重の\( \ \fbox { (7) } \ \)を想定最大張力とした\( \ \fbox { (5) } \ \)を使用する鉄塔を\( \ 1 \ \)基施設すること。
〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 5 &(ロ)& 支 線 &(ハ)& 腐 食 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 2 \ 分の \ 1 &(ホ)& 3 \ 分の \ 1 &(ヘ)& 10 \ 分の \ 1 \\[ 5pt ]
&(ト)& 不平均張力 &(チ)& 水平張力 &(リ)& 3 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 構造上安全なものとすること && &(ル)& 地形を考慮すること \\[ 5pt ]
&(ヲ)& 10 &(ワ)& 懸垂がいし装置 &(カ)& 耐張がいし装置 \\[ 5pt ]
&(ヨ)& 温 度 &(タ)& 20 &(レ)& 振 動 \\[ 5pt ]
&(ソ)& 1.25 &(ツ)& 2 &(ネ)& 径間の均衡を図ること \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第32条,電気設備の技術基準の解釈第60条及び第92条からの出題です。
条文からの抜出しの問題ですが,前半の32条は\( \ 1 \ \)種の受験生ならば確実に得点しておきたい問題,後半は半分程度は得点しておきたい問題と言えると思います。
【解答】
(1)解答:レ
電気設備に関する技術基準を定める省令第32条第1項に規定されている通り,振動となります。
(2)解答:ニ
電気設備に関する技術基準を定める省令第32条第1項に規定されている通り,\( \ 2 \ \)分の\( \ 1 \ \)となります。
(3)解答:ヌ
電気設備に関する技術基準を定める省令第32条第2項に規定されている通り,構造上安全なものとすることとなります。
(4)解答:ツ
電気設備の技術基準の解釈第60条第1項に規定されている通り,安全率は\( \ 2 \ \)以上となります。
(5)解答:ワ
電気設備の技術基準の解釈第92条第4項に規定されている通り,懸垂がいし装置となります。
(6)解答:ヲ
電気設備の技術基準の解釈第92条第4項に規定されている通り,\( \ 10 \ \)基となります。
(7)解答:ト
電気設備の技術基準の解釈第92条第4項に規定されている通り,不平均張力となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第32条>
架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は、当該支線に係るものを含む。)は、その支持物が支持する電線等による引張荷重、\( \ 10 \ \)分間平均で風速\( \ 40 \ \mathrm {m / s} \ \)の風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される地理的条件、気象の変化、(1)振動、衝撃その他の外部環境の影響を考慮し、倒壊のおそれがないよう、安全なものでなければならない。ただし、人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては、その施設場所を考慮して施設する場合は、\( \ 10 \ \)分間平均で風速\( \ 40 \ \mathrm {m / s} \ \)の風圧荷重の(2)\( \ \color {red}{\underline {2}} \ \)分の\( \ \color {red}{\underline {1}} \ \)の風圧荷重を考慮して施設することができる。
2 架空電線路の支持物は、(3)構造上安全なものとすること等により連鎖的に倒壊のおそれがないように施設しなければならない。
<電気設備の技術基準の解釈第60条(抜粋)>
架空電線路の支持物の基礎の安全率は、この解釈において当該支持物が耐えることと規定された荷重が加わった状態において、(4)\( \ \color {red}{\underline {2}} \ \)(鉄塔における異常時想定荷重又は異常着雪時想定荷重については、\( \ 1.33 \ \))以上であること。ただし、次の各号のいずれかのものの基礎においては、この限りでない。
一 木柱であって、次により施設するもの
イ 全長が\( \ 15 \ \mathrm {m} \ \)以下の場合は、根入れを全長の\( \ 1 / 6 \ \)以上とすること。
ロ 全長が\( \ 15 \ \mathrm {m} \ \)を超える場合は、根入れを\( \ 2.5 \ \mathrm {m} \ \)以上とすること。
ハ 水田その他地盤が軟弱な箇所では、特に堅ろうな根かせを施すこと。
二 \( \ \mathrm {A} \ \)種鉄筋コンクリート柱
三 \( \ \mathrm {A} \ \)種鉄柱
<電気設備の技術基準の解釈第92条>
特別高圧架空電線路の支持物に、木柱、\( \ \mathrm {A} \ \)種鉄筋コンクリート柱又は\( \ \mathrm {A} \ \)種鉄柱(以下この条において「木柱等」という。)を連続して\( \ 5 \ \)基以上使用する場合において、それぞれの柱の施設箇所における電線路の水平角度が\( \ 5 \ \)度以下であるときは、次の各号によること。
一 \( \ 5 \ \)基以下ごとに、支線を電線路と直角の方向にその両側に設けた木柱等を施設すること。ただし、使用電圧が\( \ 35,000 \ \mathrm {V} \ \)以下の特別高圧架空電線路にあっては、この限りでない。
二 木柱等を連続して\( \ 15 \ \)基以上使用する場合は、\( \ 15 \ \)基以下ごとに、支線を電線路に平行な方向にその両側に設けた木柱等を施設すること。
2 前項の規定により支線を設ける木柱等は、第96条又は第101条第2項第二号ロ若しくはハの規定により設けた支線の反対側に、更に支線を設けた木柱等をもって代えることができる。
3 特別高圧架空電線路の支持物に、\( \ \mathrm {B} \ \)種鉄筋コンクリート柱又は\( \ \mathrm {B} \ \)種鉄柱を連続して\( \ 10 \ \)基以上使用する部分は、次の各号のいずれかによること。
一 \( \ 10 \ \)基以下ごとに、耐張型の鉄筋コンクリート柱又は鉄柱を\( \ 1 \ \)基施設すること。
二 \( \ 5 \ \)基以下ごとに、補強型の鉄筋コンクリート柱又は鉄柱を\( \ 1 \ \)基施設すること。
4 特別高圧架空電線路の支持物に、(5)懸垂がいし装置を使用する鉄塔を連続して使用する部分は、(6)\( \ \color {red}{\underline {10}} \ \)基以下ごとに、異常時想定荷重の(7)不平均張力を想定最大張力とした(5)懸垂がいし装置を使用する鉄塔を\( \ 1 \ \)基施設すること。
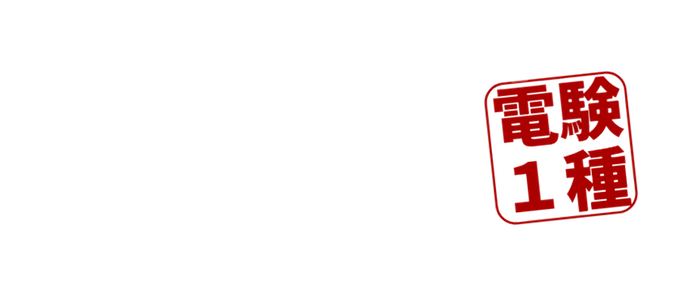
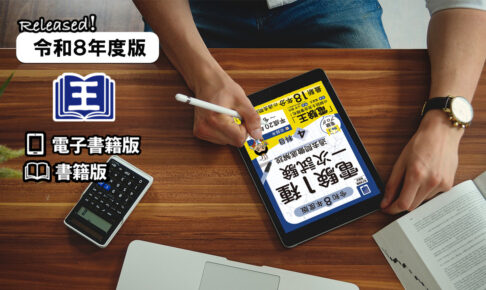
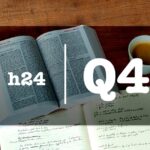
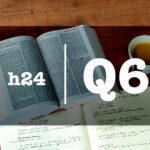
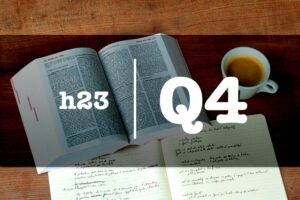
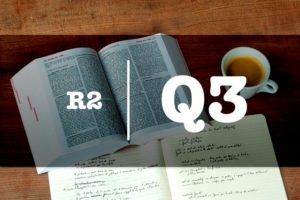
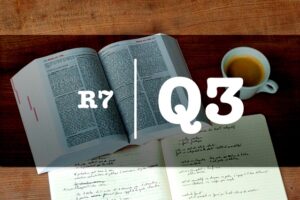
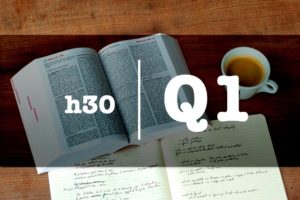
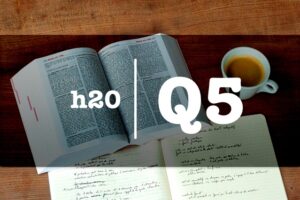
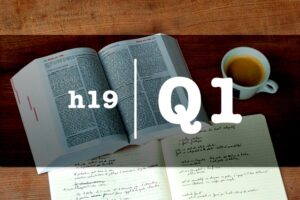
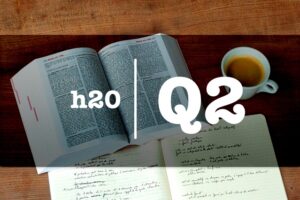
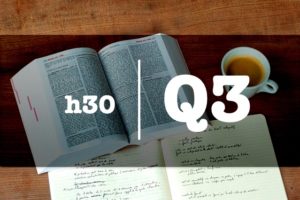

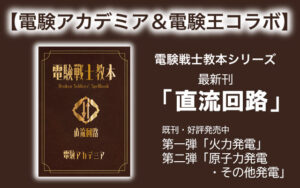
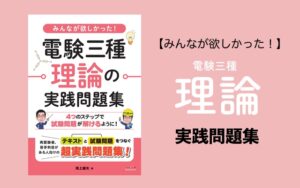
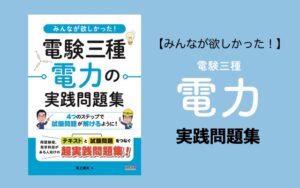
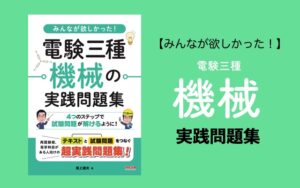
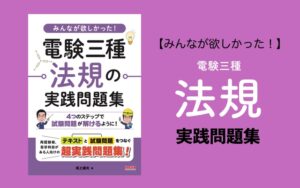




 愛知県出身 愛称たけちゃん
愛知県出身 愛称たけちゃん