Contents
【問題】
【難易度】★★★★☆(やや難しい)
次の文章は,大容量火力発電所の発電機で発生する電圧を系統電圧に昇圧する主変圧器に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切な語句を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。
低圧側電圧を発電機端子電圧にほぼ等しくすることから,低圧部には大電流が流れる。そのため,巻線漏れ磁束や巻線リードの磁界による構造部材の\( \ \fbox { (1) } \ \)への配慮が必要である。また,発電機端子電圧から系統電圧へ直接昇圧するため,\( \ \fbox { (2) } \ \)が大きい。
巻線の結線方法は,\( \ \fbox { (3) } \ \)を循環させることが可能であること,低圧側の中性点が発電機で接地できることから,\( \ \fbox { (4) } \ \)が適用される。
わが国の大容量火力発電所は,海上輸送が可能な沿岸地域に立地することが多く,重量や寸法などの輸送制約が少ないこと,また,高圧側引き出しにエレファント形接続方式を採用することが多く,絶縁距離による配置制約がないことから,\( \ \fbox { (5) } \ \)として製作されることが多い。
〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& タップ間隔 &(ロ)& 特別三相器 &(ハ)& 第 \ 5 \ 次高調波 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 三相器 &(ホ)& 低圧側 \ \Delta \ 形-高圧側 \ \Delta \ 形 &(ヘ)& 単相器 \\[ 5pt ]
&(ト)& 第 \ 3 \ 次高調波 &(チ)& 低圧側 \ \Delta \ 形-高圧側 \ \mathrm {Y} \ 形 &(リ)& 変圧比 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 局部過熱 &(ル)& 部分放電 &(ヲ)& 容 量 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 第 \ 2 \ 次高調波 &(カ)& 低圧側 \ \mathrm {Y} \ 形-高圧側 \ \Delta \ 形 &(ヨ)& 騒音発生 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
大容量火力発電所で採用される主変圧器に関する問題です。
しっかりとした中身の理解は火力発電の専門の方しかわからないかと思いますが,電磁誘導や変圧器の結線方式等から\( \ 2~3 \ \)個の空欄は埋められるかと思います。合格のためにはそれで十分と考えて良いでしょう。
1.大容量発電所の主変圧器
大容量発電所の主変圧器は発電機電圧から系統電圧に昇圧する変圧器です。
主変圧器の結線方式は一般に一次側を\( \ \Delta \ \)形,二次側を\( \ \mathrm {Y} \ \)形とした\( \ \Delta – \mathrm {Y} \ \)結線方式が採用されます。これは\( \ \mathrm {Y} \ \)結線において線間電圧が相電圧の\( \ \sqrt {3} \ \)倍で変圧比をより大きくできるためであり,その他にも第\( \ 3 \ \)調波を\( \ \Delta \ \)結線で循環させ系統側へ流出することが抑えることができること,一次側の中性点が発電機で接地できること,等の理由もあります。
また,大容量火力発電所は沿岸地域に立地することが多いため,海上輸送により搬入が可能であり,重量や寸法の輸送制約が少ないことから,主に工場で三相器として製作され現地に搬入されます。
出典:東京電力ホールディングス株式会社 HP
URL:https://www.tepco.co.jp/fukushima1-np/b43203-j.html
【解答】
(1)解答:ヌ
題意より解答候補は,(ヌ)局部過熱,(ル)部分放電,(ヨ)騒音発生,になると思います。
巻線漏れ磁束や巻線リードの磁界による電磁誘導により,構造部材には局部過熱が発生する可能性があります。
(2)解答:リ
題意より解答候補は,(イ)タップ間隔,(リ)変圧比,(ヲ)容量,等になると思います。
ワンポイント解説「1.大容量発電所の主変圧器」の通り,主変圧器は発電機電圧から系統電圧に昇圧する変圧器なので,変圧比が大きい変圧器となります。容量等も誤りとまではいきませんが,問題文と合わせより大きな特徴は変圧比となるかと思います。
(3)解答:ト
題意より解答候補は,(ハ)第\( \ 5 \ \)次高調波,(ト)第\( \ 3 \ \)次高調波,(ワ)第\( \ 2 \ \)次高調波,になると思います。
ワンポイント解説「1.大容量発電所の主変圧器」の通り,\( \ \Delta \ \)結線により,第\( \ 3 \ \)次高調波を還流することができます。
(4)解答:チ
題意より解答候補は,(ホ)低圧側\( \ \Delta \ \)形-高圧側\( \ \Delta \ \)形,(チ)低圧側\( \ \Delta \ \)形-高圧側\( \ \mathrm {Y} \ \)形,(カ)低圧側\( \ \mathrm {Y} \ \)形-高圧側\( \ \Delta \ \)形,になると思います。
ワンポイント解説「1.大容量発電所の主変圧器」の通り,主変圧器は低圧側\( \ \Delta \ \)形-高圧側\( \ \mathrm {Y} \ \)形とするのが一般的です。
(5)解答:ニ
題意より解答候補は,(ロ)特別三相器,(ニ)三相器,(ヘ)単相器,になると思います。
ワンポイント解説「1.大容量発電所の主変圧器」の通り,主変圧器は海上輸送で重量・寸法等の制約,配置制約等も少ないことから,三相器として製作されることが多いです。問題文にあるエレファント形接続方式は,高圧側引出部が象の形に似ていることからそのように呼ばれます。








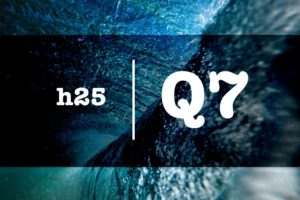

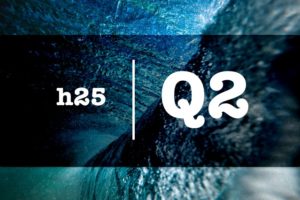
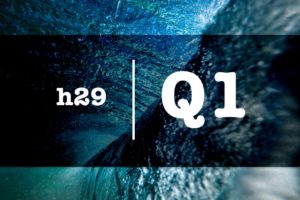

 【令和8年度版2種一次試験】
【令和8年度版2種一次試験】








 愛知県出身 愛称たけちゃん
詳しくは
愛知県出身 愛称たけちゃん
詳しくは