【問題】
【難易度】★★★★☆(やや難しい)
汽力発電所(コンバインドサイクル発電所を除く。)が系統並列運転中に,次の(1)から(3)の事象が発生した際に考えられる発電所設備への影響について,それぞれ二つ挙げ,その理由を述べよ。
(1) 系統周波数が,異常に低下した場合
(2) 系統周波数が,異常に上昇した場合
(3) 異常な進相運転が行われた場合
【ワンポイント解説】
系統周波数変動や進相運転の汽力発電設備への影響に関する問題です。
電験の過去問でも概要を扱うことはありますが,火力発電所の運転経験者以外の方はなかなかわからないような内容かと思います。
ほとんどの受験生は選択しない問題と思いますので,参考程度に見ておくようにして下さい。
1.系統周波数変動時の汽力発電プラントへの影響
同期機の回転速度\( \ N \ \mathrm {[{min}^{-1}]} \ \)は,極数を\( \ p \ \),周波数を\( \ f \ \mathrm {[Hz]} \ \)とすると\( \ \displaystyle N=\frac {120f}{p} \ \)の関係があり,系統周波数が変動すると,タービン発電機の回転速度が変動します。これにより以下の問題点が生じる可能性があります。
①タービン(特に低圧タービン)の振動
タービンの動翼の共振周波数と回転速度が共振をすることで振動が上昇する可能性があります。
②発電機の出力変動
速度調定率により周波数が変動すると出力が変化するため,周波数が低下すると出力が上昇し,周波数が上昇すると出力は低下します。
③タービン軸受油圧の低下
主油ポンプがタービン直結式のものも多いため,回転速度が低下すると軸受油圧が低下し,軸受損傷やユニットトリップに至る可能性があります。
④発電機補機の出力上昇,減退
周波数が変化すると補機の誘導電動機の回転速度が変化するため,回転速度が変化すると出力が変化します。
⑤ボイラ燃焼制御,給水制御の不安定化
補機の出力が変化するため,ボイラの燃焼制御や給水制御が不安定となる可能性があります。
⑥発電機・変圧器の過励磁
発電機や変圧器鉄心の磁束密度は\( \ V / f \ \)にほぼ比例し,\( \ V / f \ \)をほぼ一定に保つ必要がありますが,周波数が低下すると\( \ V / f \ \)が大きくなり,磁束密度が増えます。したがって,過励磁により鉄損が増加し過熱する可能性があります。
2.タービン発電機進相運転時の留意点
①固定子鉄心端部の過熱
固定子鉄心端部には電機子反作用による漏れ磁束が存在しますが,進相運転により界磁電流が減少し界磁磁束が減少すると漏れ磁束が通りやすくなり渦電流が増え,渦電流損やヒステリシス損が発生し温度上昇させます。
②定態安定度の低下
進相運転により界磁電流を減少すると,発電機内部起電力の減少,内部相差角の増大により,同期化力が低下し定態安定度が低下します。
③所内電圧の低下
発電機端子電圧の低下により,所内機器の電圧が低下します。電圧低下により大型電動機のトルク不足が発生する可能性があります。
【解答】
(1)系統周波数が,異常に低下した場合
(ポイント)
・ワンポイント解説「1.系統周波数変動時の汽力発電プラントへの影響」の通りです。
(試験センター解答例)
① 低圧タービン動翼の共振(振動,損傷)
タービン動翼の固有振動数は共振を避けるため,定格周波数の整数倍からずれるように設計されているが,低周波数運転を行うと,翼長の長い低圧タービン動翼の固有振動数と運転周波数の整数倍とが一致して共振現象を起こし,動翼に過大な応力を与える。その疲労が蓄積するとクラックが発生し,最悪の場合,翼の折損に至る。
② 発電機・変圧器の過励磁による鉄心等の過熱
発電機や変圧器の鉄心磁束密度は電圧/周波数\( \ \left( \mathrm {V / Hz} \right) \ \)の値に左右される。周波数が低下すると電圧/周波数\( \ \left( \mathrm {V / Hz} \right) \ \)の値が大きくなり,励磁電流が増加し磁束密度が増えるため,鉄心内では鉄損が増加し過熱する。また,磁気飽和の程度が過度になると鉄心から近接する導体構造物への漏えい磁束が増加し,うず電流による過熱が発生する。
③ 発電機出力の上昇
タービン調速機は,速度調定率に基づいた出力となるよう,蒸気弁\( \ \left( \mathrm {CV} \right) \ \)開度を制御している。周波数が異常に低下した場合,速度調定率に応じて蒸気弁\( \ \left( \mathrm {CV} \right) \ \)は大きく開方向に動作し,その結果,発電機出力が上昇する。
④ 発電機機内冷却能力の低下
回転子に取り付けられている冷却ファンの回転速度低下により冷却能力が低下し,機内温度の上昇や局部過熱を引き起こす。
⑤ 潤滑油等の油圧低下
タービン軸に直結した主油ポンプの回転数が低下して油圧低下を引き起こすと,軸受の油膜切れによる軸受損傷を引き起こす。また,タービン軸に直結した主油ポンプで制御油も供給している場合は,制御油圧低下によりユニットトリップに至ることもある。
⑥ 補機能力の低下
循環水ポンプなどの補機類は,誘導電動機により駆動されているため,周波数低下によって回転数が低下し,流量・圧力が低下する。なお,給水ポンプなど流量・圧力制御されている補機については,流量・圧力を規定値に維持するため,電動機の電流が増えて,電動機の過熱を引き起こす場合がある。
(2)系統周波数が,異常に上昇した場合
(ポイント)
・ワンポイント解説「1.系統周波数変動時の汽力発電プラントへの影響」の通りです。
(試験センター解答)
① 低圧タービン動翼の共振(振動,損傷)
タービン動翼の固有振動数は共振を避けるため,定格周波数の整数倍からずれるように設計されているが,周波数が異常に上昇した状態で運転を行うと,翼長の長い低圧タービン動翼の固有振動数と運転周波数の整数倍とが一致して共振現象を起こし,動翼に過大な応力を与える。その疲労が蓄積するとクラックが発生し,最悪の場合,翼の折損に至る。
② 発電機出力の低下
タービン調速機は,速度調定率に基づいた出力となるよう,蒸気弁\( \ \left( \mathrm {CV} \right) \ \)開度を制御している。周波数が異常に上昇した場合,速度調定率に応じて蒸気弁\( \ \left( \mathrm {CV} \right) \ \)は大きく閉方向へ動作し,その結果,発電機出力が低下する。
③ タービン車軸・車室などの熱応力の発生
周波数の上昇に伴い,タービン調速機の速度調定率に応じて蒸気弁\( \ \left( \mathrm {CV} \right) \ \)が絞られるため,絞り損失により主蒸気温度が急速に低下し,車室や車軸などに熱応力を生じる。
④ 主蒸気圧力の上昇(プラント制御の乱調)
周波数の上昇に伴い,タービン調速機の速度調定率に応じて蒸気弁\( \ \left( \mathrm {CV} \right) \ \)が絞られるため,主蒸気流量が減少する。蒸気流量の減少が急激な場合,あるいは主蒸気流量の減少に対応する燃料流量の絞り込みが十分でない場合は主蒸気圧力が過上昇し,ボイラトリップに至る場合がある。
(3)異常な進相運転が行われた場合
(ポイント)
・ワンポイント解説「2.タービン発電機進相運転時の留意点」の通りです。
(試験センター解答)
① 固定子鉄心端部の過熱
電機子反作用による端部漏れ磁束は鉄心端から外部に向かい,回転子保持環を通ってまた鉄心に戻る。進相運転時は電機子反作用漏れ磁束は多くなる。この磁束は,回転子に対しては静止しているが,固定子に対しては同期速度で回転しているため,固定子鉄心端部及び固定子端部構造物に渦電流損やヒステリシス損が発生し,過熱を引き起こす。
② 安定度の低下
進相運転時は,低励磁によって発電機内部誘起電圧が低下し,発電機と系統間の電圧相差角が増加し,定態安定度が低下する。なお,自動電圧調整装置\( \ \left( \mathrm {AVR} \right) \ \)を使用していれば安定運転領域が拡大され,安定度は向上する。
③ 所内電圧の低下による補機能力の低下
進相運転を行うと,発電機端子電圧が低下するため,所内の母線電圧も低下する。所内母線には多くの補機用電動機がつながっており,電圧が低下するとトルク不足により,流量・圧力が低下する。なお,流量・圧力制御されている補機については,流量・圧力を規定値に維持するため,電動機の電流が増えて電動機の過熱を引き起こす場合がある。
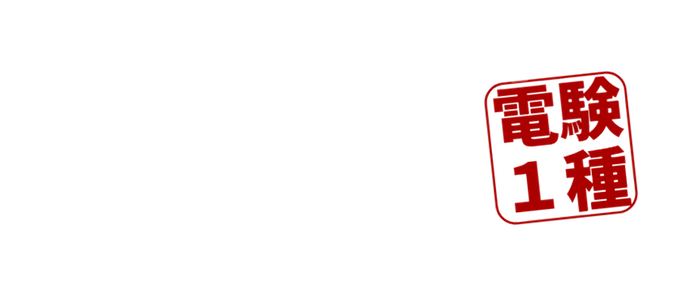
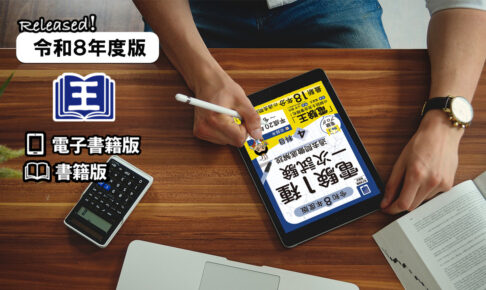











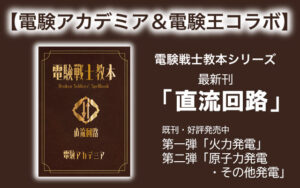
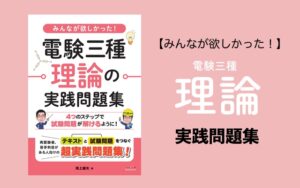
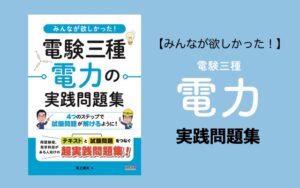
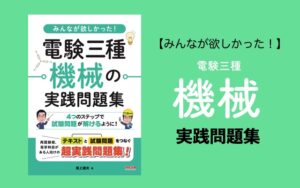
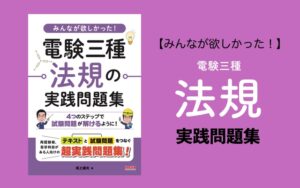




 愛知県出身 愛称たけちゃん
愛知県出身 愛称たけちゃん