Contents
【問題】
【難易度】★☆☆☆☆(易しい)
次に文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく,電圧の維持に関する記述である。
電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。)(現:一般送配電事業者)は,その供給する電気の電圧の値をその電気を供給する場所において,表の左欄の標準電圧に応じて右欄の値に維持するように努めなければならない。
\[
\begin{array}{|c|c|}
\hline
標準電圧 & 維持すべき値 \\
\hline
\ 100 \ \mathrm {V} & \ 101 \ \mathrm {V}の上下 \ \fbox { (ア) } \ \mathrm {V} \ を超えない値 \\
\hline
\ 200 \ \mathrm {V} & \ 202 \ \mathrm {V}の上下 \ \fbox { (イ) } \ \mathrm {V} \ を超えない値 \\
\hline
\end{array}
\]
また,次の文章は,「電気設備技術基準」に基づく,電圧の種別等に関する記述である。
電圧は,次の区分により低圧,高圧及び特別高圧の三種とする。
a.低 圧
直流にあっては\( \ \fbox { (ウ) } \ \mathrm {V} \ \)以下,交流にあっては\( \ \fbox { (エ) } \ \mathrm {V} \ \)以下のもの
b.高 圧
直流にあっては\( \ \fbox { (ウ) } \ \mathrm {V} \ \)を,交流にあっては\( \ \fbox { (エ) } \ \mathrm {V} \ \)を超え,\( \ \fbox { (オ) } \ \mathrm {V} \ \)以下のもの
c.特別高圧
\( \ \fbox { (オ) } \ \mathrm {V} \ \)を超えるもの
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{cccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) & (オ) \\
\hline
(1) & 6 & 20 & 600 & 450 & 6 \ 600 \\
\hline
(2) & 5 & 20 & 750 & 600 & 7 \ 000 \\
\hline
(3) & 5 & 12 & 600 & 400 & 6 \ 600 \\
\hline
(4) & 6 & 20 & 750 & 600 & 7 \ 000 \\
\hline
(5) & 6 & 12 & 750 & 450 & 7 \ 000 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
本問は電験取得者であれば,必ず理解していなければならない最重要事項であり,ほとんどの合格者が解ける問題と言っても過言ではありません。実務においても非常に重要な内容となるので,確実に理解しておきましょう。
【解答】
解答:(4)
(ア)
電気事業法施行規則第38条の表の通り,標準電圧\( \ 100 \ \mathrm {V} \ \)の時は,\( \ 101 \ \mathrm {V} \ \)の上下\( \ 6 \ \mathrm {V} \ \)を超えないように維持しなければなりません。近年太陽光発電所の普及により電圧制限の上限に達し,一時的に送電できなくなるケースがあります。
(イ)
電気事業法施行規則第38条の表の通り,標準電圧\( \ 200 \ \mathrm {V} \ \)の時は,\( \ 202 \ \mathrm {V} \ \)の上下\( \ 20 \ \mathrm {V} \ \)を超えないように維持しなければなりません。
(ウ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第2条の通り,直流にあっては\( \ 750 \ \mathrm {V} \ \)で低圧と高圧に分かれます。
(エ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第2条の通り,交流にあっては\( \ 600 \ \mathrm {V} \ \)で低圧と高圧に分かれます。交流が直流よりも低いのは,交流の波高値が実効値の\( \ \sqrt {2} \ \)倍になることからであると考えられます。
(オ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第2条の通り,\( \ 7 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)で高圧と特別高圧に分かれます。
<電気事業法施行規則第38条>
法第26条第1項(法第27条の12の13及び第27条の26第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
\[
\begin{array}{|c|c|}
\hline
標準電圧 &維持すべき値 \\
\hline
100 \ \mathrm {V} & 101 \ \mathrm {V} \ の上下 \ \color{red}{\underline {(ア) \ 6 \ } \ }\mathrm {V} \ を超えない値 \\
\hline
200 \ \mathrm {V} & 202 \ \mathrm {V} \ の上下 \ \color{red}{\underline {(イ) \ 20 \ } \ }\mathrm {V} \ を超えない値 \\
\hline
\end{array}
\]
2 法第26条第1項の経済産業省令で定める周波数の値は、その者が供給する電気の標準周波数に等しい値とする。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第2条>
電圧は、次の区分により低圧、高圧及び特別高圧の三種とする。
一 低圧 直流にあっては(ウ)\( \ \color{red}{\underline {750}} \ \)\(\mathrm {V} \ \)以下、交流にあっては(エ)\( \ \color{red}{\underline {600}} \ \)\(\mathrm {V} \ \)以下のもの
二 高圧 直流にあっては(ウ)\( \ \color{red}{\underline {750}} \ \)\(\mathrm {V} \ \)を、交流にあっては(エ)\( \ \color{red}{\underline {600}} \ \)\(\mathrm {V} \ \)を超え、(オ)\( \ \color{red}{\underline {7 \ 000}} \ \)\(\mathrm {V} \ \)以下のもの
三 特別高圧 (オ)\( \ \color{red}{\underline {7 \ 000}} \ \)\(\mathrm {V} \ \)を超えるもの
2 高圧又は特別高圧の多線式電路(中性線を有するものに限る。)の中性線と他の一線とに電気的に接続して施設する電気設備については、その使用電圧又は最大使用電圧がその多線式電路の使用電圧又は最大使用電圧に等しいものとして、この省令の規定を適用する。
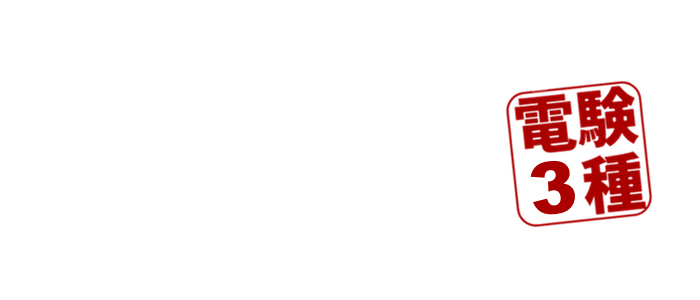




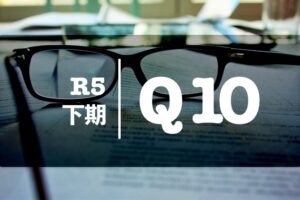

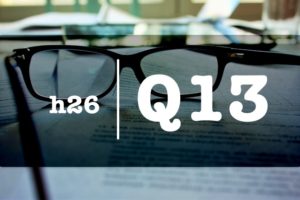

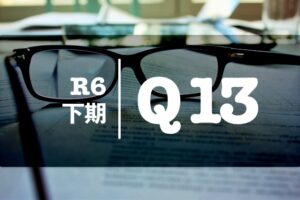


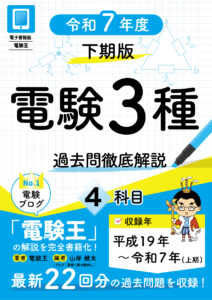
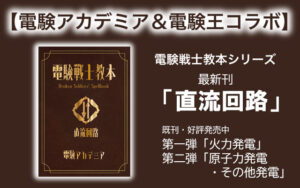
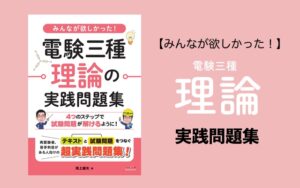
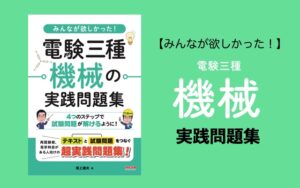
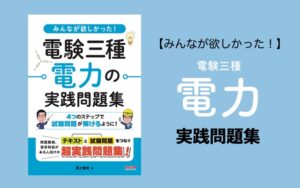
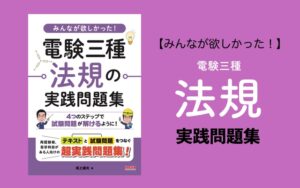




 愛知県出身 愛称たけちゃん
詳しくは
愛知県出身 愛称たけちゃん
詳しくは