Contents
【問題】
【難易度】★★★★☆(やや難しい)
次の文章は,ナトリウム-硫黄電池に関する記述である。
大規模な電力貯蔵用の二次電池として,ナトリウム-硫黄電池がある。この電池は\( \ \fbox { (ア) } \ \)状態で使用されることが一般的である。\( \ \fbox { (イ) } \ \)極活性物質にナトリウム,\( \ \fbox { (ウ) } \ \)極活性物質に硫黄を使用し,仕切りとなる固体電解物質には,ナトリウムイオンだけを透過する特性がある\( \ \fbox { (エ) } \ \)を用いている。
セル当たりの起電力は\( \ \fbox { (オ) } \ \mathrm {V} \ \)と低く,容量も小さいため,実際の電池では,多数のセルを直並列に接続して集合化し,モジュール電池としている。この電池は,鉛蓄電池に比べて単位質量当たりのエネルギー密度が\( \ 3 \ \)倍と高く,長寿命な二次電池である。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{cccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) & (オ) \\
\hline
(1) & 高温 & 正 & 負 & 多孔質ポリマー & 1.2~1.5 \\
\hline
(2) & 常温 & 正 & 負 & ベータアルミナ & 1.2~1.5 \\
\hline
(3) & 低温 & 正 & 負 & 多孔質ポリマー & 1.2~1.5 \\
\hline
(4) & 高温 & 負 & 正 & ベータアルミナ & 1.7~2.1 \\
\hline
(5) & 低温 & 負 & 正 & 多孔質ポリマー & 1.7~2.1 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
ナトリウム-硫黄電池(\( \ \mathrm {NAS} \ \)電池)に関する問題です。
電験のテキストではあまり掲載されていない内容で,受験生にはかなり厳しい問題であったかと思います。
電力貯蔵用の蓄電池として有名であるため,雑学として勉強されていた方はラッキーであったかと思います。
1.ナトリウム-硫黄電池
ナトリウムと硫黄を溶融状態にして運転することから「ナトリウム-硫黄電池(\( \ \mathrm {NAS} \ \)電池)」と呼ばれます。鉛蓄電池に比べて体積や質量が小さく,資源が豊富で長寿命であることから大電力貯蔵用設備として実用化されています。
①材料(反応式は暗記不要です)
正 極:硫黄
負 極:ナトリウム
電解質:\( \ \beta \ \)-アルミナ
②特徴
・鉛蓄電池に比べ,エネルギー密度が約\( \ 3 \ \)倍となりコンパクトにできる
・昼夜間の負荷平準化として都市部近郊に揚水発電と同様な機能を設けることが可能
・出力変動の大きい太陽光発電や風力発電と組合せ出力の安定化を図ることが可能
・停電時の非常用電源としても利用可能
・希少金属を使用せず,資源が豊富で長寿命
・自己放電が少ない
・セルあたりの起電力は\( \ 1.7~2.1 \ \mathrm {V} \ \)程度とあまり高くないため,セルを直並列して使用する必要がある
・作動温度が\( \ 300 \ \)℃程度と高い温度を維持する必要がある
・火災事故が発生した際,水消火をするとナトリウムと水が反応してしまうため,消火活動が容易でない
【解答】
解答:(4)
(ア)
ワンポイント解説「1.ナトリウム-硫黄電池」の通り,ナトリウム-硫黄電池は一般に\( \ 300 \ \)℃程度の高温状態で使用されます。
(イ)
ワンポイント解説「1.ナトリウム-硫黄電池」の通り,ナトリウムは負極活性物質となります。
(ウ)
ワンポイント解説「1.ナトリウム-硫黄電池」の通り,硫黄は正極活性物質となります。
(エ)
ワンポイント解説「1.ナトリウム-硫黄電池」の通り,固体電解質にはベータアルミナ(\( \ \beta – \mathrm {Al_{2}O_{3}} \ \))を使用します。
(オ)
ワンポイント解説「1.ナトリウム-硫黄電池」の通り,セル当たりの起電力は\( \ 1.7~2.1 \ \mathrm {V} \ \)となります。
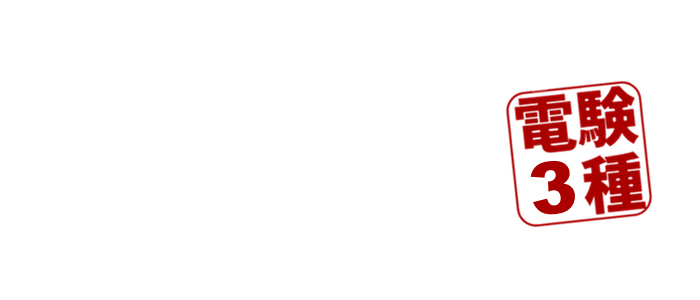











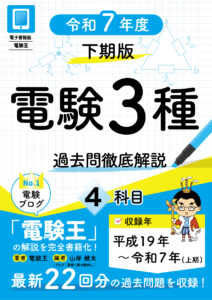
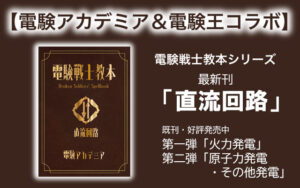
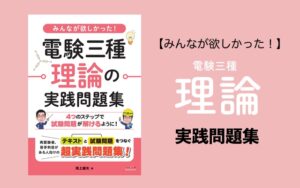
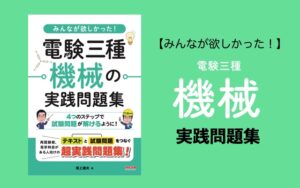
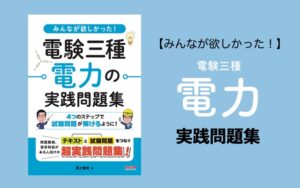
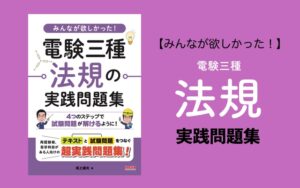




 愛知県出身 愛称たけちゃん
詳しくは
愛知県出身 愛称たけちゃん
詳しくは